はじめに
仕事選びって、誰にとっても大切なこと。
でも発達特性をもつ私にとっては、「働きやすいかどうか」=生きやすさそのものに直結していました。
私はこれまで、雰囲気や条件だけで職場を選んで何度も失敗してきました。
でもその経験を重ねたことで、「自分に合う環境ってどんなものだろう?」という視点が育ってきた気がしています。
最初の就職先でのギャップ(コンビニ編)
最初に働いたのはコンビニ。
「レジと品出しができればOKかな」と軽く考えていました。
でも実際には、レジ業務だけでもタスクが山盛り。
公共料金の伝票処理、チケットの発券、宅配の受付、レジ金の管理、揚げ物の注文…と、とにかく同時に考えて動く場面が多すぎてパンク寸前でした。

しかも、ミスをするとそのままお客様に迷惑がかかる。
焦ってテンパって、さらにミスを繰り返してしまう悪循環に。
メモを取っていても、順番を間違えたり、やったかどうかを忘れてしまうことが多くて、正直つらかったです。
最終的には数ヶ月でスピード対応もできるようになり、即戦力とは言われましたが…
数字関係の処理だけは最後まで苦手で、「そこはやらない」と割り切るようになりました。
転職でうまくいったかと思いきや…(パチンコ店編)
その次に選んだのは、パチンコ店のホールスタッフ。
雰囲気がやさしそうだったのと、接客中心ならいけるかな…という感覚で選びました。
でも実際には、抽象的な指示+即時の判断が求められることが多く、混乱しっぱなし。
「何となく察して動いてほしい」という場面が多く、空気を読むことが苦手な私には、うまく動けない場面ばかりでした。
さらにスタッフの人数も多く、お局さんとパートさんの間に入るような板挟みもあり、気を遣いすぎて体調を崩してしまいました。

うまくいった転機の職場(貿易商社編)
転機となったのは、ある貿易商社で企画や営業に携わる仕事を始めたことでした。
この職場では:
- 少人数で、役割分担が明確
- 必要なやりとりはしっかり伝え合う文化があった
- 人間関係もさっぱりしていて、お互い干渉しすぎない
さらに大きかったのは、在宅ワークが基本だったこと。
出社は、月に数回だけ(定期ミーティング、営業対応、重要書類を扱う時など)。
それ以外は、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、自分の集中できる環境を選べる働き方だったんです。
「今日は家で集中しよう」
「今日は気分転換にカフェで仕事しよう」
そんなふうに、自分の状態に合わせて働けることが、本当に心地よかったです。
自分の強みに気づけたきっかけ
業務に慣れてきた頃、私はMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)資格を取得しました。
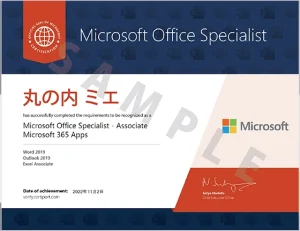
ネットやPC関連の作業に関しては、“頭が回るタイミング”が合っていたのか、比較的スムーズに学ぶことができました。
その後は、社内で営業や企画運営といった業務も任されるように。
元々、創造力や発想力には自信があったので、
「やっと自分の良い部分を活かせている」と実感できたのは、この職場が初めてだったかもしれません。
働きやすさ=“配慮”じゃなく“相性”だった
たくさんの職場を経験して気づいたのは、
「働きやすさ」って、“配慮”があるかどうかじゃなくて、**「自分にとってその環境が合っているかどうか」**だということ。
私に合っていたのは:
- 静かで落ち着いた空間
- 業務ルールが明確
- 一人で集中して取り組める作業
- 指示が具体的で共有がていねい
逆に、複数人チームで空気を読みながら進めるタイプの職場では、だんだん疲れがたまってしまいます。
だから私は、プロジェクトに関わる場合でも、「得意な分野かつ、一人で集中して進められる役割」を選ぶように調整しています。
終わりに
私は、就職や職場選びで何度も失敗してきました。
でも今思えば、それは「向いていなかった」のではなく、
**「自分に合った働き方をまだ知らなかっただけ」**なんです。
今、やっと「これは自分に合っている」と感じる働き方に出会えているのは、
あの時の失敗があったからこそ、自分を知るチャンスが生まれたんだと思います。
もし今、働きづらさを感じている人がいたら、
「それって、あなたのせいじゃなくて、“その環境と合ってないだけ”かもしれないよ」って、そっと伝えたいです。









